IPランドスケープとパテントマップの違い
知財系 もっともっと Advent Calendar 2021の枠が空いていたので、ネタ記事として投稿しました。
Googleで「IPランドスケープ パテントマップ」と入力すると、「違い」がサジェストされます。
知財業界ではよく議論になってるし、気になってたり、もやっとしてる人が多いんじゃないかと思います。
IPランドスケープとは
知財スキル標準によれば「パテントマップとは異なり、自社、競合他社、市場の研究開発、経営戦略等の動向および個別特許等の技術情報を含み、自社の市場ポジションについて現状の俯瞰、将来の展望等を示すものである」と定義されてます。
特許庁の制度研究によれば、「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有すること」と定義されてます。
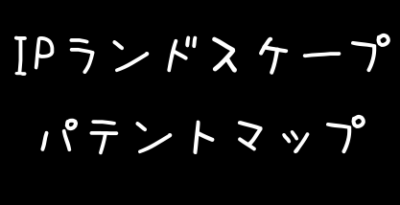
よく言われるパテントマップとの違い
取り扱う情報の違い:パテントマップは特許情報だけを使うのに対して、IPランドスケープは知財情報と非知財情報、特に経営情報を使うという点。
目的の違い:パテントマップは動向調査などの場面に限られていたのに対して、IPランドスケープは新規事業・用途探索や提携先等候補探索など様々な経営戦略の目的に使われるという点。
レポートラインの違い:パテントマップは知財部門向けが中心であったのに対して、IPランドスケープは経営層や事業責任者に向けたものだという点。
みたいなことが、パテントマップとの違いとして聞くことが多いです。
違いに対する反論
パテントマップを作って分析すること、特許分析とか技術動向分析とかマクロ分析とか言われていたと思いますが、
実際にこの時代の分析でも、非特許文献をソースとして使うことはよくありました。論文とかニュースとか。また、経営情報を加味しない企業内の分析とか、あり得ないでしょう。
目的としても、各種用途探索や将来予測としても使われていましたし、経営や事業戦略に影響を与える目的じゃなく分析してた人っているんでしょうか。
レポートラインとしても、経営レポート、事業部やR&D向けの分析も多々ありました。
上記の点が違うと言われると、いや昔からやってたでしょ、と突っ込みたい気持ちが抑えきれません。
直訳的には、パテントマップが一つのアウトプットを、IPランドスケープが分析することを指すので、パテントマップを作ることもIPランドスケープの一つじゃん、本質的には変わらないでしょ?と言いたくなります。
IPランドスケープの考え方が重要であることは間違いありませんが、その説明のためにパテントマップを貶める表現をされると、昔からやってる人間からするとピクピクっとしてしまうのです。
名前が変わることはよくある
ところで、同じようなものの名前が変わることって、他にもよくありますよね。
ユビキタスと言われていたものがIoTになって一気に流行ったり、
IT化と言われていたものがDX化に変わって簡単に稟議が下りたり、
ロビイングと言われていたものがパブリックアフェアーズに変わっていい感じの雰囲気に見えたり。
他にもいろいろあります。
もちろんこれらの言葉の変化には微妙な定義の違いもあって、
DX化とIT化の違いは「デジタル化を手段と捉えるか、目的と捉えるか」みたいに言われたり、パブリックアフェアーズはロビイングよりもオープンで公益性のあるアプローチを目指すと言われたりします。
これに対して、いやロビイングだって公益性のある活動もしてたとか、IT化だって目的をもってやってるだろとか言っても仕方ないですね。
時代、期待感、文脈が違う
IPランドスケープも、時代が変わって、それに期待されるものや文脈が微妙に変わっていった結果、受け皿として新しい名前が求められたという類のものだと思います。
なので、IPランドスケープとパテントマップの何が違うかというと、時代が変わったし、そこに求められる期待感が違うし、文脈が変わってきている、という微妙な違いでしかないんだと思います。
もう少しかみ砕くと、「本質的には変わらないけど、パテントマップと言われていた時代に比べると、IPランドスケープは比較的特許以外の情報も組み合わされる傾向にあり、経営へのレポートや事業戦略への影響がより期待され、知財経営のような文脈で使われることが多い」という違いでしょうか。
違いを高らかに主張するのは無知に見えるけど、いちいち反論するのは無粋
これが違うよ、と言われると突っ込みたくなる気持ちは沸いてくるのですが、いちいち反論するのは無粋なんでしょうね。
IoTが流行った時代に「ユビキタスと変わらんやん」っていうのは無粋だし、メタバースが流行ろうとしている時代に「セカンドライフがあったやん」っていうのも無粋だし。
無知というのは言葉が悪くて、たぶん一部の人は、それらを全部分かった上で、「こんな説明を求めてるんでしょ?」とIPランドスケープの新しさ(⇒パテントマップの古さ)を提示してるんだと思います。
なので、言葉や定義の違いみたいな小さいところは気にせずに、知財部・情報分析に期待される考え方が時代と共に変わってきてるんだなくらいに受け止めるのがいいんだと整理しています。
IPランドスケープが従前から変わらず重要であること自体は誰も否定しないと思うので、みんなでIPランドスケープやっていきましょう。
関連記事
-

-
無形資産ではなく、特許のことは特許と言おうぜ
アドベントカレンダーに空き枠があったので、たまにはとりとめのないことでも書いてみ …
-
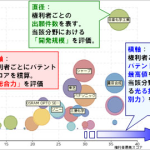
-
特許のスコアリング・指標 ~特許の質評価・分析~
特許の評価(価値評価)と言う時、大きくは定性評価と定量評価に分かれ、定量評価の中 …
-

-
2年ぶりの特許フェアの哀愁
特許・情報フェア&コンファレンス行ってきました! 2020年の特許フェアはオンラ …
-

-
2019年の振り返り
今年も残りあと僅かですね。皆さんにとって2019年はどうだったでしょうか? 私は …
-

-
湯浅竜×IPFbiz ~知財教育と最強の知財マン~
対談シリーズ第13回目は、弁理士の湯浅竜さんです。前回の野崎さんからご紹介いただ …
-

-
Googleの新しい取り組み”Google Patent Starter Program”は、パテントトロールからスタートアップを守るのか
Googleは最近、パテントトロール対策のための団体「LOTネットワーク」を設立 …
-

-
齋藤憲彦 × IPFbiz ~Appleに特許で勝った個人発明家~ (前編)クリックホイール発明秘話
対談シリーズ第19回目は、iPodのクリックホールに関する特許訴訟で、Apple …
-
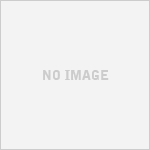
-
独占性と排他性:独占排他権の誤解
特許権は、「独占排他的な権利」であると言われます。 独占的であり、かつ排他的であ …
-

-
法制度改正と特許出願(技術書典)
技術書典(エンジニアのコミケ)に、技術と法律チームで出展して、薄い本を出します。 …
-
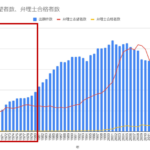
-
知財業界の歴史と未来
”歴史を振り返って、過去から現在までの時の流れに思いを巡らせてごら …
