法制度改正と特許出願(技術書典)
技術書典(エンジニアのコミケ)に、技術と法律チームで出展して、薄い本を出します。新井さんお誘いありがとう。
私は「法制度改正と特許出願」というテーマで執筆予定で、とりあえず、はじめにと終わりにだけ書いたので部分的に公開しちゃいます。
全編読みたい方、また他の魅力的な共同執筆者の原稿も読みたい方は、ぜひ技術書典に参加して買ってください。
というか、まだ中身となる具体的な特許のピックアップが出来てないので、テーマに沿ったいい特許ご存知の方、教えてください。
==========================
1.はじめに
技術と法律には密接な関係があります。 技術が変われば世界が変わる、その世界に合わせて法制度も変わる。
例えば。 インターネットという技術が登場したことにより、世界は大きく変わりました。それによって様々な法律が改正を余儀なくされましたが、大きく影響を受けたのは著作権法です。インターネットの登場により著作物の利用方法はこれまで想定されていなかった様々な態様に及び、そのために著作権の権利制限規定はそれぞれの利用態様ごとに追加され、多くの実務家を悩ませました。
他にも、ブロックチェーンという技術の登場により、仮想通貨が生まれ、資金決済などの実世界に大きな影響を与えています。これに対応すべく、通称仮想通貨法と呼ばれる資金決済法の改正がなされましたが、まだまだ新たな課題への法制度改正の対応を余儀なくされています。
例を挙げればきりがありません。ドローンの登場により航空法が改正されましたし、自動運転技術の登場により道路交通法の改正が求められています。AIの進化がさらなるスピードで発展することによっても、きっと様々な法制度に影響を与えるでしょう。
そう、通常は、先に技術が変わり、それを追いかける形で法律が変わります。 しかし、実はその逆も存在するのです。 本稿では、法制度の改正をきっかけとした新たな技術(特許発明)に着目しようと思います。
法制度が変わることにより、これまでは出来なかったサービスが出来るようになる。それを実現するための技術が必要となり、新しい特許発明が生まれる。 または、法制度が変わることにより、これまでは不要だった新たな仕様をクリアする必要が生じ、それを解決するための特許発明が生まれる。このように、法制度改正をきっかけとして新たな特許発明が生まれることはままあります。
特許を取りうるような進歩性のある発明を創出するには、新しい「課題」を発見・設定することが重要です。例えば、コスト低減のような普遍的な課題を設定すると、よほど特異な解決手段を発見しない限り特許権取得は難しいですが、課題自体に新規性があるようなものを課題設定することにより、ある程度当たり前の解決手段を適用するだけで、進歩性のある発明を創出することができます。
つまり、法制度改正というのは、有用な特許発明を創出するのに非常に良いきっかけであり、テーマ設定となり得るものです。次項で、その具体例を見てみましょう。
2.法制度改正と新しい特許出願の例
未定です。いい特許の例があったら教えてください。。
例えば、免税制度改正に対応した特許第6112279号、特許第6267096号や、
生活保護制度改正に対応した特許第6063510号、
薬剤師常駐を不要とする登録販売者試験制度に対応した特許第5783299号
などの紹介を考えていますが、もっといい例ありそう。
他にも、遠隔医療制度がらみに対応した特許や、電力自由化に対応した特許や、酒税法改正に対応するための新しいビールの作り方の特許とか、きっとあると思うのですが、見つけ切れていません。
3.まとめと提言
以上のように、法制度改正を一つのきっかけと捉え、新たな課題を設定することで、新制度に対応する発明について有意義な特許の取得を狙うことができます。
いや、それだけではつまらないので、もっと踏み込んで考えてみましょう。法制度の改正は国会で閣議決定され公布されます。その公布を見ることで、新たな課題がセットされ、各社よーいドンで開発競争が始まる。本当にそうでしょうか。通常は国会に上がる前に、審議会などで議論がされます。そのような審議会の最新の議論を常にウォッティングする、あるいはそのような情報に詳しい会社の部署と密接なコンタクトを持つことで、よーいドンではなく他社に先駆けて新制度に対応する発明の開発に着手することができます。
また、審議会での議題に上がるということは、それ以前に世論として制度改正のニーズが生じているという事です。それを踏まえて、法制度改正の先読みをすることで、より早い段階でスタートを切ることができます。さらに踏み込んで考えれば、法制度は所与のものとして与えられるのではなく、ロビイングにより変えることができるものです。新しい社会のためにロビイングをしながら、その裏で必要となる仕様を組み込んだ発明の特許出願をしておけば・・というのは少し黒すぎるでしょうか。
どこまで踏み込んで動くかはともかく、法制度改正に対応して、またはそれを予想して新たな課題を設定することで、より強い特許権の取得ができることは間違いないでしょう。
関連記事
-

-
当業者とは何か? 特許の進歩性の便宜的な考え方
当業者とは何か? 初学者が最初の頃に疑問に思うことですね。 当業者とは発明の属す …
-

-
進歩性に思いを馳せる
「知財系 Advent Calendar 2024」初日の記事です! 何を書くか …
-

-
齋藤憲彦 × IPFbiz ~Appleに特許で勝った個人発明家~ (前編)クリックホイール発明秘話
対談シリーズ第19回目は、iPodのクリックホールに関する特許訴訟で、Apple …
-

-
2019年の振り返り
今年も残りあと僅かですね。皆さんにとって2019年はどうだったでしょうか? 私は …
-

-
特許情報フェアの歩き方
さて、来週はいよいよ特許フェアですね。特許フェア初心者の方のために、特許フェアの …
-
基本特許とは何か。基本特許の例/リスト[弁理士の日記念]
本日7/1は、弁理士の日らしいです。弁理士だけど知らなかった。ということで、ドク …
-

-
IT系知財のオープンな勉強会やります。 ~気になる特許について語ろう会(第1回)~
これまで、事務所内で定期的に勉強会をやってきました。過去の事例で中間対応案考えて …
-
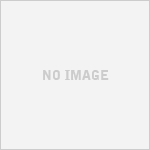
-
独占性と排他性:独占排他権の誤解
特許権は、「独占排他的な権利」であると言われます。 独占的であり、かつ排他的であ …
-

-
齋藤憲彦 × IPFbiz ~Appleに特許で勝った個人発明家~ (後編)訴訟裏話と知財司法の課題
前編からの続きです。アップルとのコンタクトから訴訟へきっかけは母親の発明?安高: …
-

-
2018年の振り返りと、2019年の抱負
一年の計は元旦にあり!私の好きな言葉です。昨年の振り返りと今年の目標を、しっかり …

