進歩性に思いを馳せる
「知財系 Advent Calendar 2024」初日の記事です!
何を書くか悩んでいたのですが、特にいいネタが思いつかず。。
そして執筆中のもので「進歩性とは」というのを書く必要があったので、進歩性について思いを馳せながら、つらつらと書いてみることにしました。
進歩性とは
進歩性とは、特許法第49条に規定される特許要件の一つであり、第29条第2項に下記のように規程されている。
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
かみ砕くと、
「当業者が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたものか否か」
という要件である。
法律の規定のみでは、当業者がどの程度の創作能力を有しているのか、容易に発明をすることができるとはどの程度の容易性なのか、判断に「幅」のある特許要件となっている。
実際の審査実務については審査基準に下記のように説明がされている。
審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし・・・主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。
最近の判例は特に、合理的な論理付けができるか否かの判断が重要視されていると感じる。つまり、材料としての構成要件が引例に記載されているかだけではなく、課題や動機付け、阻害要因の有無が重要となる。
論理付けとは、主引用発明から出発して、副引用文献の技術事項などを組み合わせて本願発明に到達する「ストーリー」を作ることができるのかどうかということだ。ストーリーを作る際には、そこにどのような課題があり、どのような動機付けがあるのかが大事になる。
私は特許庁にて先輩に下記のような考え方を教わった。
当業者の上に、天から主引用文献と副引用文献がヒラヒラと振ってくる。それを読んだ当業者が通常に思いつく複数の発明のうちの一つが、本願発明と同じになるか否かである。
一つの分かりやすい捉え方かと思う。
進歩性と後知恵
進歩性の判断をするうえで、「後知恵」に陥ることがないように審査官は留意しなければならないとされる。
具体的には審査基準において、
(i) 当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたように見えてしまうこ
と。
(ii) 引用発明の認定の際に、請求項に係る発明に引きずられてしまうこと
の2点が留意点として挙げられている。
後知恵とは何か。
審査は本願発明をよく理解したうえで行われるので、「事後的判断」となることは避けられない。事後的判断と後知恵とは異なるのか。
審査の進め方は、論理付けに最も適した、つまり最も本願発明を拒絶しやすいような主引用発明を選んだうえで、拒絶をするための論理付けを行っていくため、後知恵であることは避けられないようにも思われる。
しかし、ここで具体的に問題とされている後知恵とは、
(i) 当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたように見えてしまうこと。
⇒根拠のない進歩性の否定をしてはならない。上述の判断の流れに従って論理付けができるか否かを検討しなければならない。あるいは出願時の技術常識に基づいて判断をしなければならない。
(ii) 引用発明の認定の際に、請求項に係る発明に引きずられてしまうこと
⇒引用発明を過度に上位概念化したり必須で一体不可分の構成事項を捨象するような引用発明認定をしてはならない。
ということだ。
つまり、引用文献の選択に際しては、当然、後知恵で最も都合の良い文献を選択して構わない。
その認定と論理付け(それらの引用文献から自然に発想される組み合わせの発明が作られるストーリー作成)を審査基準に従って行うべしということである。
進歩性を制する者は特許実務を制する
特許実務において、最も重要性が高い特許要件は進歩性だと考える。拒絶査定となった特許出願の拒絶理由の実に85%が進歩性によるものであり、他の拒絶理由と比べると適用割合は群を抜いている(※審査官ラボ調べ)。
また、その他の形式的な拒絶理由とは異なり、中間対応の場面だけでなく発明を権利化するか否かの判断やそのブラッシュアップ、アイデア出しの場面においても進歩性的思考で検討を行うという点で、進歩性の知識は汎用的なものである。
そのような点から、進歩性を制する者は特許実務を制すると言えるのではないだろうか。
進歩性は実務入門者の最初の壁であり、周りと差をつけるポイントである
弁理士試験の勉強と、弁理士実務のトレーニングとは少し異なる。したがって、弁理士資格は取得しているが実務的には入門ということが多々ある(他の士業に比べると弁理士は特にそういう側面があると感じる)。
その中でも特に入門者が躓くポイントが進歩性の判断であろう。資格の勉強で身に着けた知見を用いて、さあ進歩性の判断をしてみよと言われても、まあ難しい。なんなら、審査基準をしっかり通読した後ですら、やはり難しい。
だからこそ、進歩性の知識をしっかり身に着けているかどうかは、周りと差をつけることができる強いポイントである。これば弁理士にも限らず、例えばサーチャーであっても、進歩性のロジックを理解しているサーチャの先行技術調査の結果と、そうでないサーチャーの結果とは、出てくる文献に違いがある。発明発掘なども上述の通りである。
また、ベテラン風の人であっても、会話をしていると実は進歩性の中身を理解していないなと感じることがある。
入門者の壁であり、差をつけるポイントでもあり、奥の深い領域でもある。
進歩性は特許制度の番人である
法律の規定のみでは進歩性の判断に幅があると上述した。そしてこの「幅」こそが特許制度の制度目的を果たすことができるか否かに影響を与える重要な要素になり得る。
特許制度の目的は産業の発達であるが、権利化のハードルを下げすぎてしまうと、かえって発明の社会実装を妨げ、産業の発達を阻害してしまう。
特許権を与える発明に、出願時の技術常識からどの程度の技術レベルの高さを求めるのか。その「程度」によっては特許制度が産業を発達させることもあれば、その逆の結果にもなりかねない。そういった点から、進歩性は特許制度の有効性を握る要素であり、「特許制度の番人」とも言えるだろう。
そして、その「程度」は時代によっても変わり得る。
ITが全業種に複雑に関係するようになった今、進歩性のハードルは同じでいいのか、生成AIにより発明活動が推進されるとすれば進歩性のハードルは同じでいいのか。
生成AIの今後の発達によっては、特許制度というもの自体が時代にそぐわなくなる将来も来るであろう。ただ、いきなり特許制度をなくすか否かという1,0の議論ではなく、進歩性のハードルがどうあるべきかという調整の議論が必要となるのではないだろうか。 ということで、進歩性に関することを色々書いてみましたが、まとまってない感じですみません。。
ということで、進歩性に関することを色々書いてみましたが、まとまってない感じですみません。。
明日のいなぽんさんにパスします。
関連記事
-

-
プロダクト・バイ・プロセスクレームの憂鬱 最高裁判決解説
プロダクト・バイ・プロセスクレームの最高裁判決が出ました。製法が異なれば特許侵害 …
-

-
サーチャー酒井美里×IPFbiz ~特許調査のプロフェッショナル~
対談シリーズ第10回は、スマートワークス(株)代表でスーパーサーチャーの酒井美里 …
-

-
2020年の抱負
一年の計は元旦にあり! ということで、毎年恒例、今年の目標です。 ちなみに、昨年 …
-

-
IT系知財のオープンな勉強会やります。 ~気になる特許について語ろう会(第1回)~
これまで、事務所内で定期的に勉強会をやってきました。過去の事例で中間対応案考えて …
-
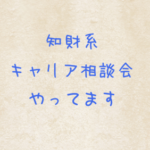
-
知財キャリア相談 よくある質問
知財系キャリア相談やってます。 気づけば1年過ぎて、40人ほどの知財系キャリア相 …
-

-
無形資産ではなく、特許のことは特許と言おうぜ
アドベントカレンダーに空き枠があったので、たまにはとりとめのないことでも書いてみ …
-

-
今年の振り返りと来年の展望 ~会社を退職して独立開業します!~
今年も「法務系 Advent Calendar」に参加させていただきました!法務 …
-

-
特許無償開放 トヨタ自動車とテスラの違い
年明け早々からビッグな知財ニュースです。 トヨタ自動車が、燃料電池自動車に関する …
-
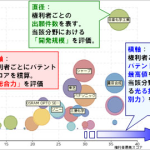
-
特許のスコアリング・指標 ~特許の質評価・分析~
特許の評価(価値評価)と言う時、大きくは定性評価と定量評価に分かれ、定量評価の中 …
-
基本特許とは何か。基本特許の例/リスト[弁理士の日記念]
本日7/1は、弁理士の日らしいです。弁理士だけど知らなかった。ということで、ドク …
- PREV
- 子供のころの勉強とかの話
- NEXT
- 2024年の振り返り
